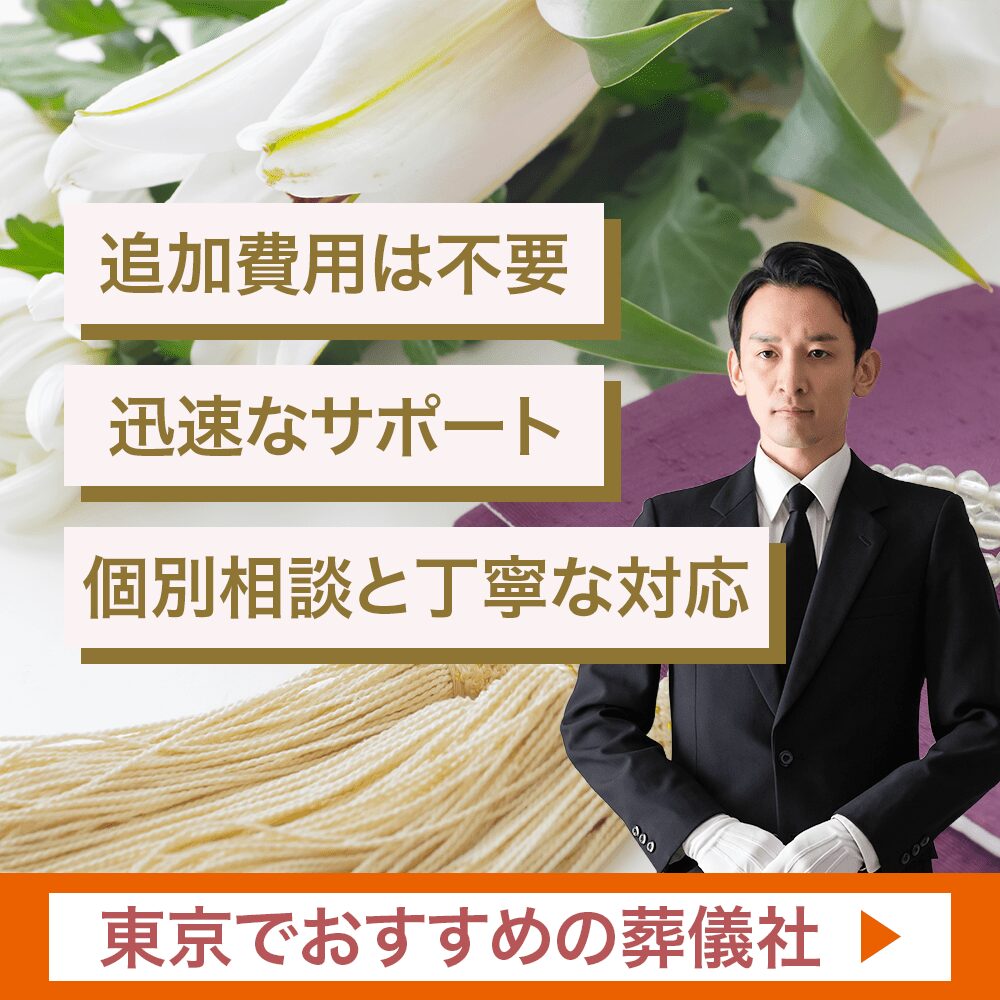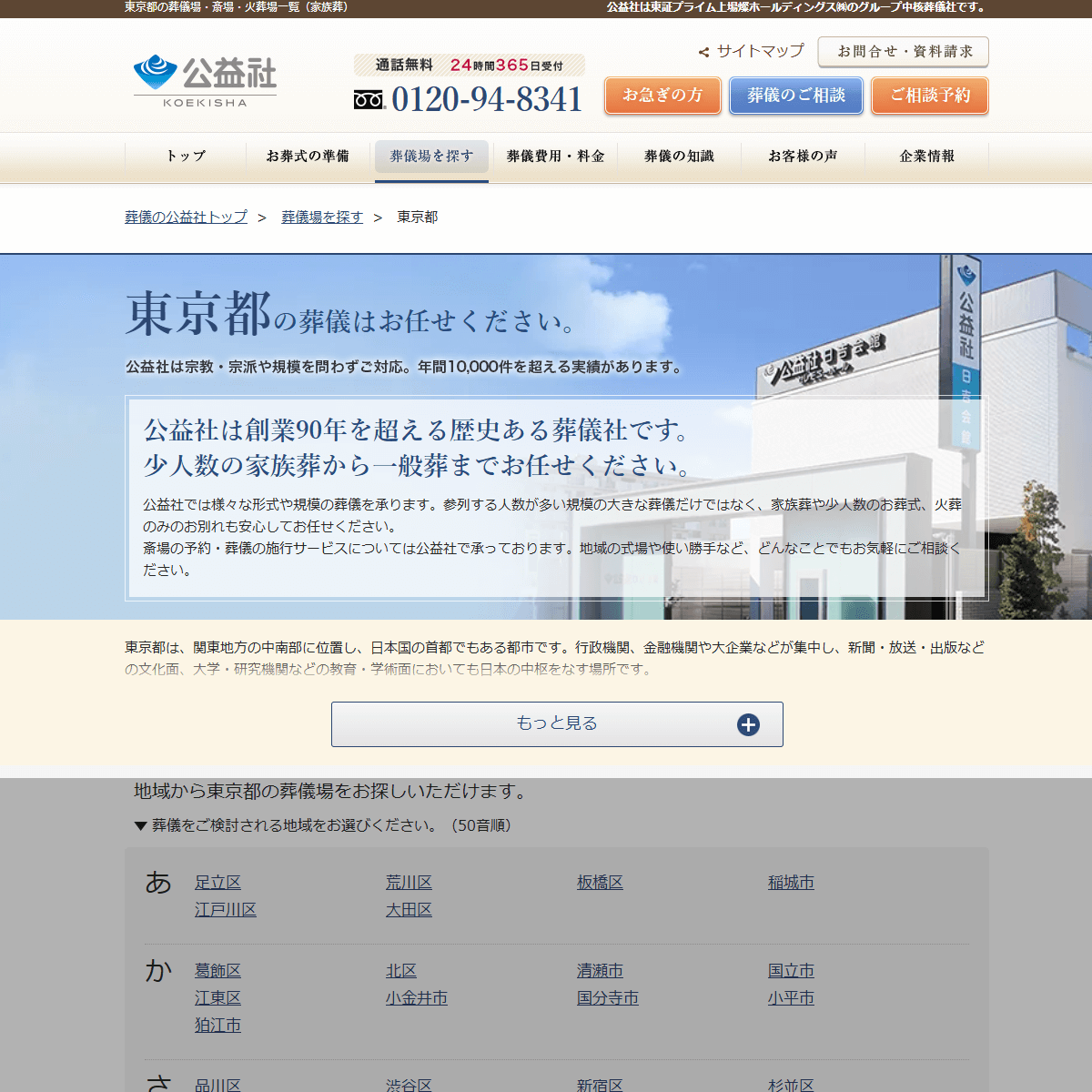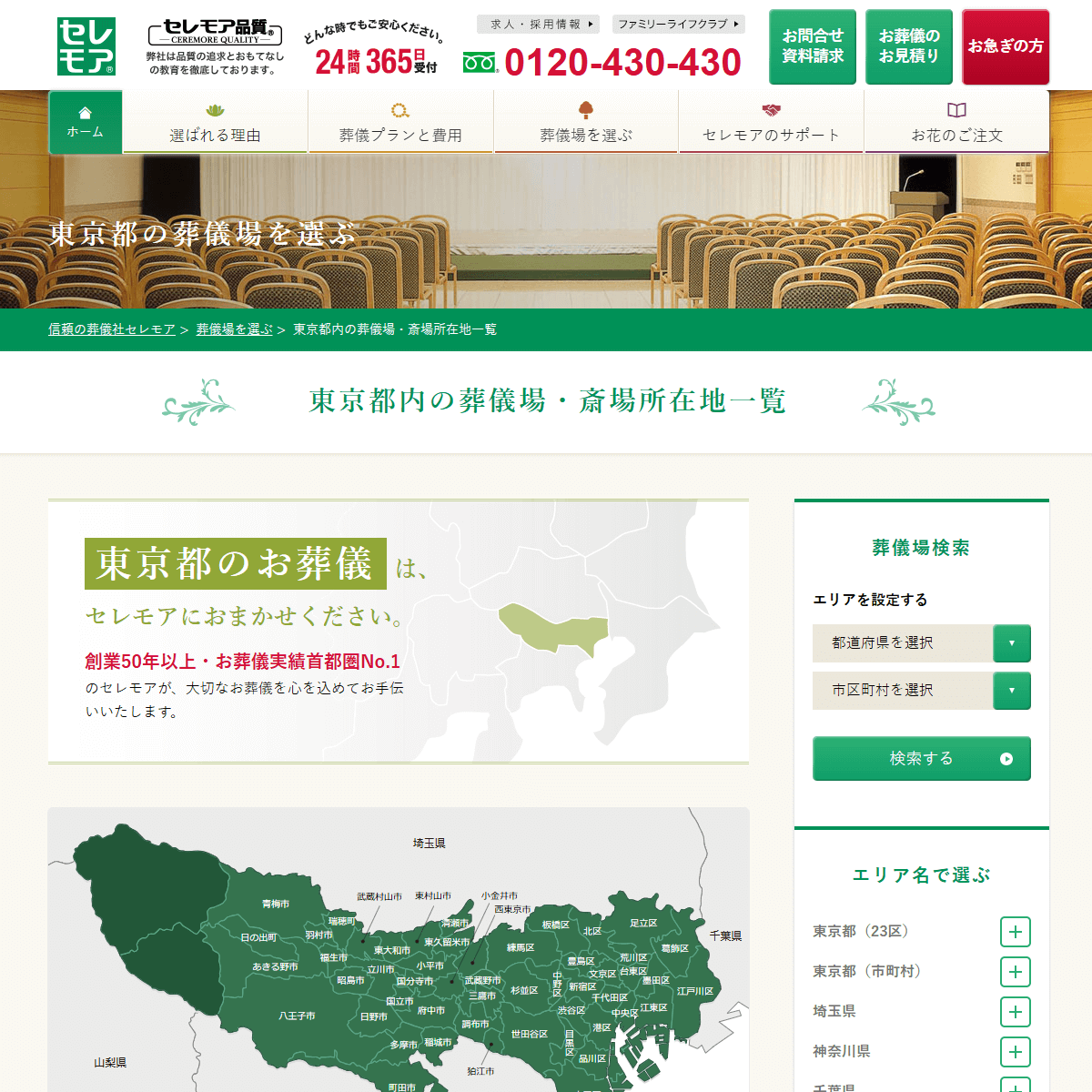大切な家族との別れは辛いですが、いざというときに慌てないようしっかり備えておきたい、という方も多いのではないでしょうか。家族の死亡後には、やらなければならないさまざまな手続きがあります。本記事では家族が亡くなった後の手続きについて詳しく紹介します。ぜひ参考にしてください。
臨終後すぐに必要な手続きとは?
家族の臨終後は、すぐに死亡診断書・死体検案書の受け取りや訃報連絡などの手続きが必要です。死亡診断書・死体検案書の受け取り
病院で亡くなった場合は、担当医師から死亡診断書を受け取ります。死亡診断書はその後のさまざまな手続きに必要な書類のため、何枚かコピーして保管しましょう。自宅など病院以外で亡くなった場合は、すぐに書類を受け取れません。警察による検視などの死因特定の手続きを経て、死体検案書が発行されます。死体検案書は、医師が人の死亡を医学的・法律的に証明する書類です。死亡診断書・死体検案書を受け取った後、自宅や葬儀社の施設、火葬場の霊安室などに遺体を搬送します。
親族や知人への訃報連絡
親族や知人への訃報連絡は、故人の意向を尊重することが大切です。事前にリストを作成しておくと連絡がスムーズです。葬儀社を決定する
家族内で相談して葬儀社を決定します。病院から紹介される葬儀社は費用が高くなるケースもあるため、慎重に判断しましょう。死亡後の手続きスケジュール
死亡後の手続きスケジュールについて解説します。死亡後1週間以内に行う手続き
死亡後2日目には、死亡届と火葬許可申請書を故人の死亡地・本籍地・届人の住所登録がある土地のいずれかの市区町村役場に提出します。火葬許可申請書とは、火葬許可証をもらうための申請書です。火葬許可書がない場合は、法律違反にあたるため火葬できません。葬儀後には遺体を火葬場に運ぶため、死亡届の提出と火葬許可証の受け取りは、葬儀前に済ませます。一般的に死亡した翌日にはお通夜、3日目には葬儀・告別式が執り行われます。火葬後は、火葬許可証に火葬の執行を証明する印が押され、遺骨と一緒に渡されるので大切に保管しましょう。用紙は、納骨の際に必要です。近年では、故人の死亡後7日目に行われる初七日法要を葬儀・告別式当日にまとめて行うケースが増えています。
死亡後2週間以内にする手続き
故人が年金を受給していた場合は、受給権者死亡届(報告書)を年金事務所もしくは街角の年金事務センターに提出します。届出には、故人の年金証明と住民票などの死亡の事実を明らかにできる書類を添付します。年金の支給停止の手続きをしないまま故人の年金を受け取ることは、不正受給にあたるため返還の必要が生じます。国民年金は死亡日から14日以内、厚生年金は死亡日から10日以内の期間内に手続きします。故人が生前にマイナンバーを取得していれば、手続きは不要です。故人が国民健康保険に加入していた場合は、死亡後14日以内に市区町村役場へ国民健康保険資格喪失届を提出し、保険証を返却しましょう。
故人が40歳以上65歳未満で要介護・要支援の認定を受けていた場合は、市区町村役場へ介護保険資格喪失届を提出し、介護保険被保険者証を返却します。故人が世帯主の場合は、死亡後14日以内に市区町村役場へ世帯主変更届を提出し、新しい世帯主を届け出ます。
世帯に誰も残されていなかったり、新しい世帯主が明確だったりと、提出不要なケースもあるため確認が必要です。
死亡後1~4か月以内にする手続き
故人が雇用保険を受給していた場合は、死亡日から1か月以内にハローワークで雇用保険受給者資格証の返還手続きをします。返還手続きには、雇用保険受給者資格証と死亡診断書か死体検案書、住民票が必要です。故人が生前に確定申告していた場合は、死亡日から4か月以内に相続人が代わりに確定申告しなければなりません。年の途中で死亡した場合、相続人が1月1日から死亡した日までに確定した所得金額および税額を計算して申告・納税する手続きを準確定申告と呼びます。
葬儀後をスムーズに進めるためのポイント
葬儀後をスムーズに進めるためのポイントを紹介します。葬儀後の煩雑な手続きを代行業者に依頼する方法もあります。スケジュールを立てて管理する
家族が亡くなった後の手続きは、多岐にわたります。手続きしないと受け取れない給付金もあるため、スケジュールを立ててチェックしながら進めましょう。書類の管理を徹底する
手続きに必要な書類を紛失しないように、管理を徹底します。重要な書類が見つからずに再発行するケースも少なくありません。しかし、再発行に時間がかかると、期限内に手続きが完了できなくなる可能性もあります。コピーをとったり、専用ファイルにまとめたりして、紛失しないように管理しましょう。代行業者に依頼する
費用はかかりますが、煩雑な手続きを代行業者に依頼することもできます。経験豊富な代行業者であれば、安心して任せられるでしょう。まとめ
この記事では、家族が亡くなった後の手続きについてお伝えしました。死亡診断書もしくは死体検案書の受け取りや葬儀社の決定など、死亡後の手続きにはさまざまなものがあります。葬儀前後の手続きをスムーズに進めるためには、スケジュールを立ててチェックしながら進めることが大切です。重要な書類については、管理を徹底して紛失を防ぎましょう。家族の死亡後の手続きについて不安を抱える方もいるかと思います。その場合、経験豊富な代行業者への依頼を検討してみてはいかがでしょうか。-
 引用元:https://gc-tokyo.co.jp/
ワンランク上のおもてなし!
引用元:https://gc-tokyo.co.jp/
ワンランク上のおもてなし!
世界に一つだけのオーダーメードの葬儀が叶う-
Point
明瞭な料金体系で追加費用が不要
-
Point
ご遺族に寄り添う個別相談と丁寧な対応
-
Point
東京・神奈川に密着し迅速なサポートを提供
-
Point