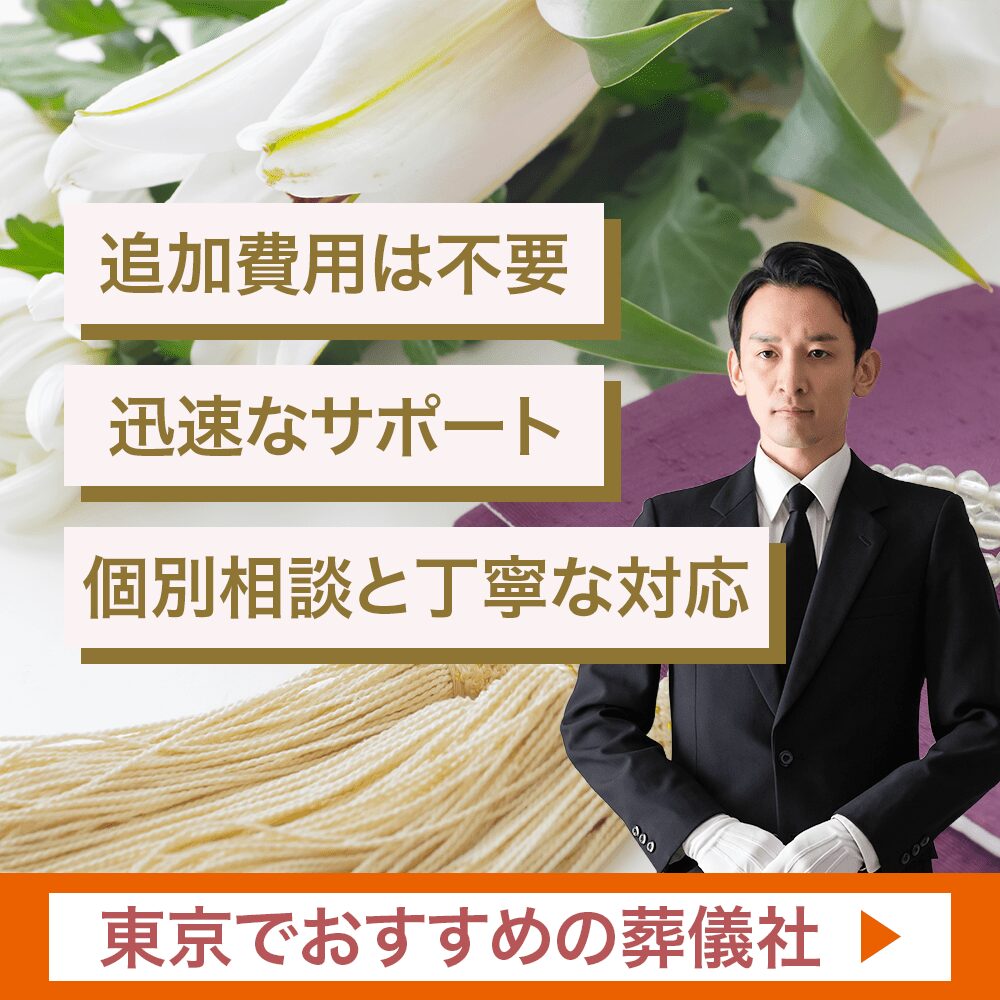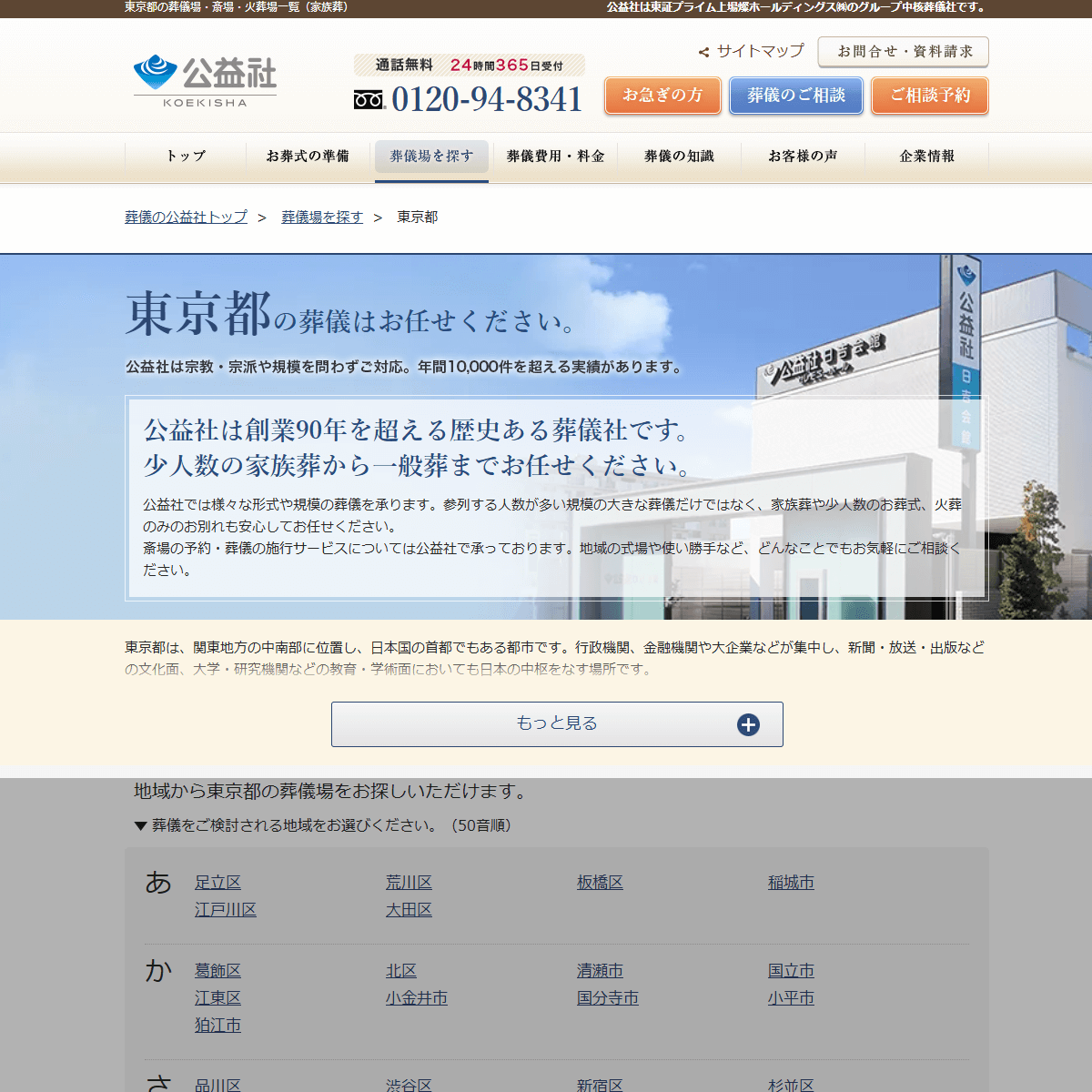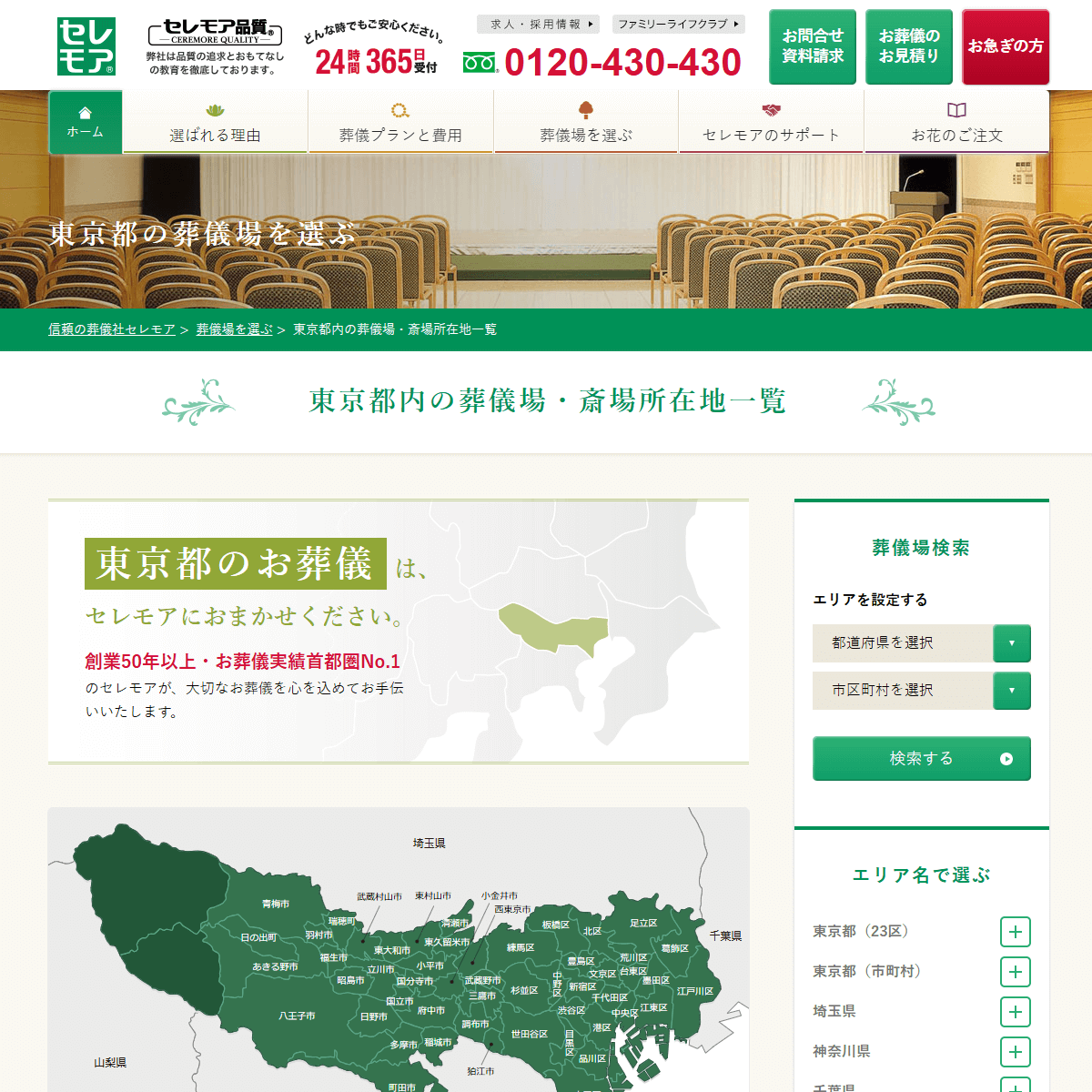葬儀は故人を偲び、遺族や参列者が想いを交わす大切な場です。形式ばかりに縛られる必要はありませんが、葬儀に関する最低限のマナーを知っておくと、不要なトラブルを招くことなく、心やすらかに故人を送れます。この記事では葬儀のマナーや礼儀作法について、各ステップごとに徹底解説します。
葬儀の基本マナー
葬儀の基本マナーは、故人への敬意を示し、遺族への配慮を忘れないことが大切です。以下のポイントを押さえて、適切な行動を心掛けましょう。服装のマナー
服装は葬儀における基本的なマナーのひとつです。参列者は喪服を着ることが求められます。喪服は黒を基調とし、これは「死」や「静けさ」「沈黙」を象徴しています。男性は黒のスーツに白いシャツ、黒のネクタイ、黒い靴を着用します。女性は黒いワンピースやスーツに黒いストッキング、光沢のない黒い靴やバッグが一般的です。子どもは黒やグレー、紺色の地味な服装、または制服が適しています。
アクセサリーはパール一連のネックレスが許容されますが、華美なアクセサリーや香水、サンダルは避けるべきです。また、髪型やメイクも控えめにすることが求められます。
挨拶とふるまい
葬儀の場では、挨拶やふるまいにも配慮が必要です。声のトーンは小さく、落ち着いた話し方を心掛け、冗談や明るすぎる話題は避けましょう。故人や遺族に関する不用意な発言も控えます。会場では私語を控え、携帯電話は電源オフまたはマナーモードに設定し、周囲への配慮を忘れないようにしましょう。
席順
葬儀会場では、席の順番にもマナーがあります。遺族席が最上座とされ、故人との関係が深い人から順に座ります。遺族や親族の席に座る場合はとくに配慮が必要です。一般的には、故人に近い関係者が前方に座り、その後に遠い親戚や友人が座ることになります。
時間厳守
葬儀は、時間を守ることが非常に重要です。葬儀の開始時刻の15~30分前には到着するのが理想的です。遅刻しそうな場合は、事前に葬儀社や喪主に連絡を入れて、対応をお願いすることが大切です。葬儀という厳粛な場で、時間に遅れることは失礼にあたるため、できる限り早めに到着するよう心がけましょう。
弔問・弔電・香典・焼香のマナー
弔問・弔電香典・焼香のマナーについて、以下のポイントに分けて解説します。弔問・弔電のマナー
弔問では、故人に対する哀悼の意を表し、遺族に対しても静かで配慮のある態度を心掛けます。挨拶は「ご愁傷さまです」などの言葉を使います。弔電は葬儀に参列できない場合に送るもので、簡潔で丁寧な表現が求められます。「お悔やみ申し上げます」などの言葉を選び、繰り返し表現や不適切な言葉は避けましょう。
香典のマナー
香典は故人への弔意を表し、遺族への経済的支援を意味する金銭です。香典を包む際は、新札を避けて古札を使うのがマナーとされています。もし古札が準備できない場合は、新札にひと折りを入れて使用し、準備していた感を和らげます。金額は故人との関係により異なり、友人の場合は5,000円~1万円、親族の場合は1万~5万円程度が相場です。
しかし、地域や家族の慣習によって変わることがあるため、気になる場合は同じ立場の人に相談するのがよいでしょう。香典袋は派手なデザインを避け、宗教に合った表書きを選びます。
たとえば仏教式には御香典」や「御霊前」、神式には「御玉串料」、キリスト教式には「御花料」が使われます。香典は通常、受付で記帳時に渡し、記帳はフルネームで丁寧に行います。香典袋は袱紗から取り出し、表書きを相手に向けて両手で渡し「このたびはご愁傷さまです」と一礼します。
焼香のマナー
焼香は仏教の儀式で、焼香の作法は宗派によって異なります。焼香を行う際は、名前を呼ばれたら静かに前に進み、合掌して一礼し、焼香を行います。数珠は基本的に左手にもち、合掌時には両手にかけて丁寧に扱うことが求められます。数珠を手首に巻いたまま焼香したり、右手にもったりすることはマナー違反です。焼香を終えたら静かに席に戻ります。
葬儀後のマナーと注意点
葬儀後には「精進落とし」と呼ばれる食事会が行われることが多いです。この場は、故人を偲び、悲しみを共に分かち合う時間です。精進落としの始まりには献杯(けんぱい)という儀式が行われ、静かな乾杯をします。グラスを合わせることなく、声も控えめに行うのが作法とされています。
遺族側は、参列者に感謝の気持ちを伝えるため、丁寧に食事の案内やお礼の言葉を述べることが大切です。参列者側は、たとえ食欲がなかったとしても、すすめられた料理には少しでも手をつけるよう心掛けましょう。
また、会話においては、明るすぎる話題や世間話を避け、故人の思い出を語ったり、遺族に寄り添うような言葉をかけることが望ましいとされています。
節度を保つふるまい
精進落としの席では、緊張がほぐれて飲酒が進みがちですが、葬儀の延長であることを忘れないようにしましょう。大声で笑ったり、盛り上がりすぎたりすることはマナー違反です。「静かに、短めに、節度をもって」という基本姿勢を意識し、場にふさわしい雰囲気を保つことが大切です。
香典返しと礼状
葬儀後の大切なマナーのひとつは香典返しです。これは、忌明け(仏教であれば四十九日)を迎えたタイミングで、香典をいただいた人々にお礼の品を贈る風習です。香典返しの目安として、いただいた香典の半額程度を返礼品として用意し、挨拶状(礼状)を添えて送るのが一般的で、丁寧な対応とされています。返礼品には、タオルやお茶、カタログギフトなど、日持ちする物や消え物(使えばなくなる物)が好まれます。
また、地域や宗教の習慣によっては、即日返しの習慣がある場合もありますので、葬儀社などに相談しながら対応するとよいでしょう。
まとめ
葬儀のマナーや礼儀作法について解説しました。服装は喪服で故人を悼む気持ちを表し、髪型やメイクは控えめを心掛けましょう。明るい話題や冗談は避け、小さな声で落ち着いて喋ることが基本です。香典は、故人との関係性によって相場額が変わります。同じような立場の方の金額を参考にして、古札を包みましょう。焼香は宗派によってやり方が異なるので、他の参列者のやり方をよく見て真似るか、焼香の案内や係の人がいる場合は従いましょう。葬儀のマナーに自信がなくても、一番大切なのは「静かに、誠意をもって故人に向き合う気持ちと姿勢」です。形式が多少異なっても、心を込めて故人を送る気持ちが大切です。-
 引用元:https://gc-tokyo.co.jp/
ワンランク上のおもてなし!
引用元:https://gc-tokyo.co.jp/
ワンランク上のおもてなし!
世界に一つだけのオーダーメードの葬儀が叶う-
Point
明瞭な料金体系で追加費用が不要
-
Point
ご遺族に寄り添う個別相談と丁寧な対応
-
Point
東京・神奈川に密着し迅速なサポートを提供
-
Point