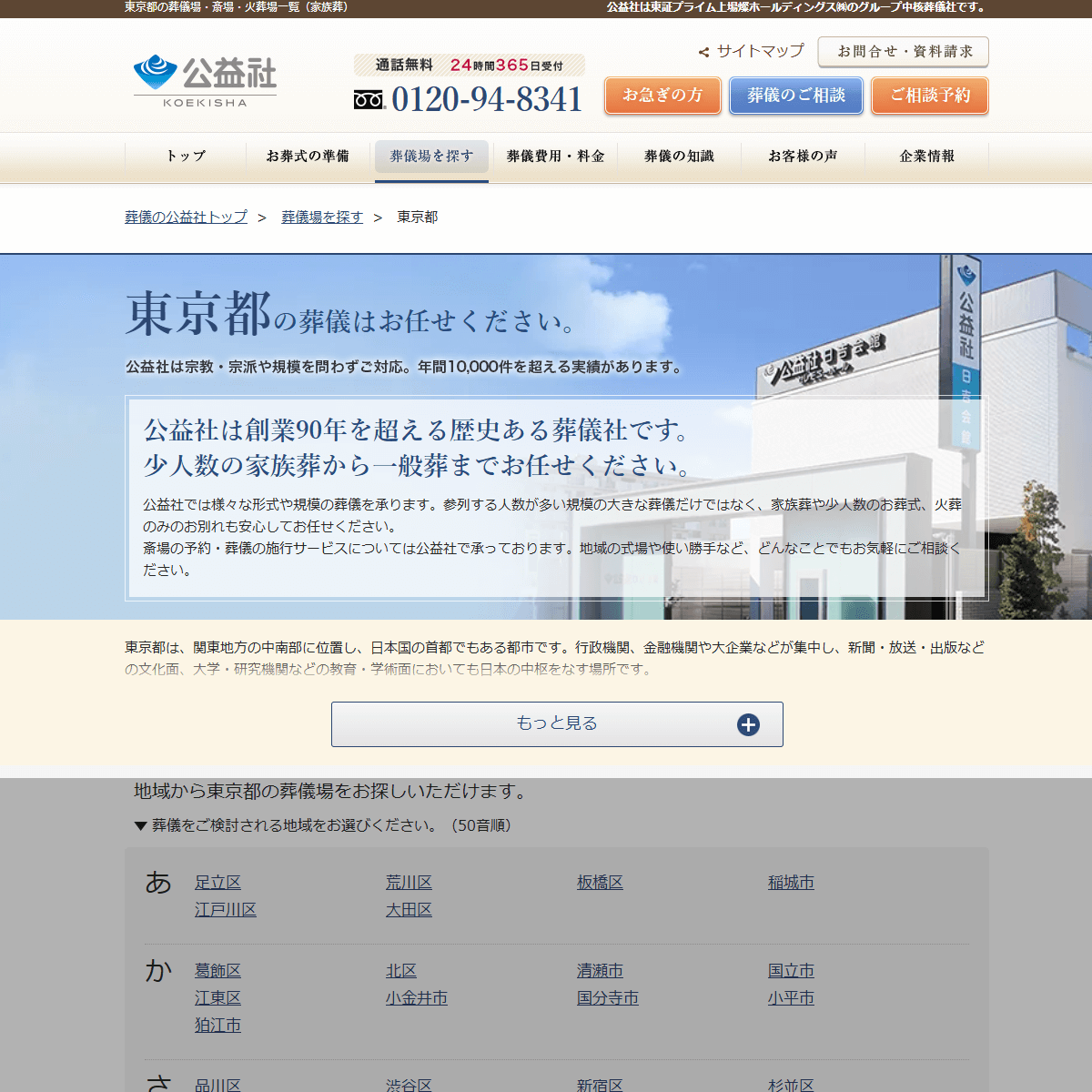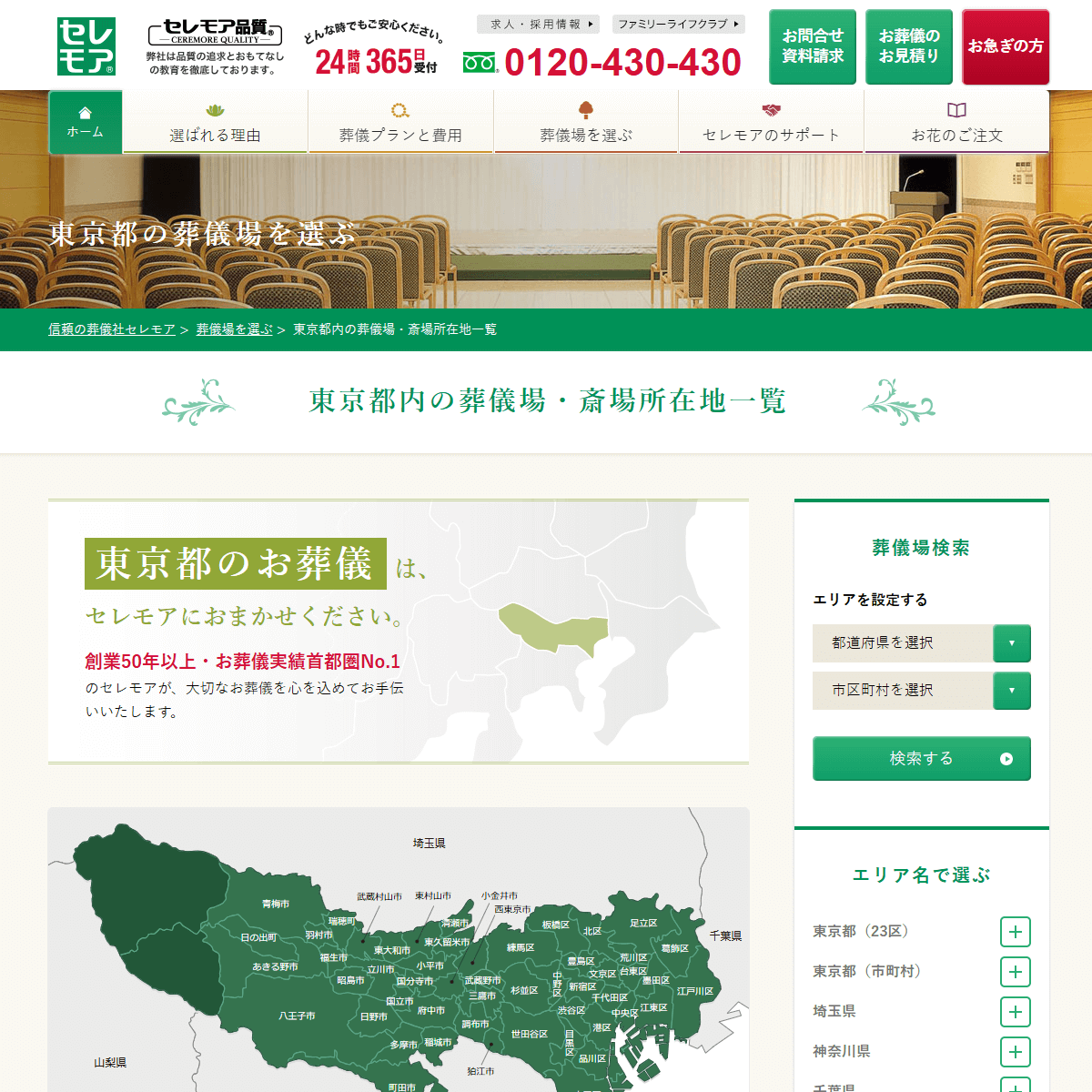香典返しをする際は、どのタイミングでどのような品物を贈ればよいのかや、贈る形式についても悩んでしまう人が多いでしょう。今回は香典返しについて、概要やタイミング、金額相場や品物の選び方、マナーなどを詳しく解説します。掛け紙や挨拶状の書き方についても紹介するため、葬儀を控えている人は参考にしてみてください。
香典返しとは?
香典返しには独自のマナーがあるため、意味や贈るタイミングをしっかりと押さえておくことが重要です。しかし、香典返しを用意する機会は多くないため、マナーについてあまり詳しくないという人も少なくないでしょう。ここでは、香典返しの意味やタイミングなどを解説します。
そもそも香典返しとは
香典返しとは、故人のお通夜や葬儀の参列者に対して渡すお返しの品です。葬儀の参列者はご霊前に香典として金銭を備えるため、遺族がお返しとして香典返しの品物を渡すという流れです。香典は家族を失った遺族を励ます・突然の出費を支える意味があり、香典返しには参列者への感謝、四十九日法要を終えた報告などの意味があります。
会葬御礼品との違い
会葬御礼品とは、弔問客が足を運んでくれたことに対するお礼の品です。そのため、参列者全員に渡すのがマナーです。対して、香典返しはあくまでも香典に対するお返しであるため、香典をもらった参列者にのみ渡すのが大きな違いとなります。
香典返しのタイミング
先述の通り、香典返しは四十九日が終わったことを参列者に対して報告するための贈り物でもあります。基本的には、四十九日を終えてから1か月以内に送るのがマナーとされています。従来は喪主が相手先の自宅を訪問して香典返しを渡すのが一般的でしたが、近年では挨拶状とともに郵送にて送るケースがほとんどです。さらに、お通夜・葬儀などで香典をもらった際にその場で香典返しを渡す、即日返しを取り入れる人も増えています。
香典返しの金額相場と贈る品物の選び方
香典返しを選ぶ際は、品物の金額相場や選び方に悩む人も多いでしょう。ここでは、香典返しの金額相場と贈る品物の選び方について詳しく解説します。香典返しの金額相場
香典返しの金額は、受け取った香典の金額によっても異なります。基本的には香典の半分の金額を目安とする半返しで問題ないため、たとえば香典として1万円をいただいた場合は5,000円相当の品物を返しましょう。地域によっては3分の1返しを慣習としているケースもあるため、迷った場合は葬儀社などに相談してみるとよいでしょう。さらに、親族などから高額な香典を受け取った場合には、半返しでなく3分の1や4分の1の金額で品物を用意しても問題ありません。
ただし、即日返しの場合は香典返しの金額を調整するのが難しいため、2,000〜3,000円程度の香典返しを用意しておきましょう。そして、1万円以上の香典をもらった際には、後日追加で香典返しを郵送するのがよいでしょう。
香典返しに向いている品物
香典返しでは、食べ物や消耗品などの消え物を選ぶのが定番です。お茶やコーヒー、お菓子のほか、せっけんや洗剤などを選ぶのがよいでしょう。また、白装束で現世から旅立つという意味から、白いタオルやシーツなどを贈る場合もあります。一方で、最近では参列者側で好きな品物を選択できるカタログギフトも人気を集めています。
香典返しのマナーと注意点
香典返しには、掛け紙や挨拶状の書き方に関するさまざまなマナーがあるため注意が必要です。ここでは、香典返しのマナーについて詳しく解説します。掛け紙の書き方
香典返しの掛け紙は弔事に使用するものであり、黒白の結び切りの水引が印刷されています。地域や宗派によっても掛け紙の種類が異なるケースがありますが、迷った場合は黒白の結び切りを選択するのが無難です。郵送の場合は内掛け・手渡しの場合は外掛けにしましょう。表書きは志が一般的ですが、地域によってはその他の表書きを使用する場合もあるため注意してください。
西日本では満中陰志、中国・四国・九州地方では茶の子と書くケースが多いです。また、表書きに使う墨は四十九日を過ぎるまでは薄墨を、四十九日以降は黒い墨を選択しましょう。
挨拶状の書き方
香典返しには、挨拶状を添えるのがマナーです。挨拶状には、香典のお礼・弔事を終えた報告・故人とのお付き合いについての感謝・香典返しの説明・略儀のお詫びを記載します。季節のあいさつや句読点、忌み言葉などは使うのは避けましょう。まとめ
今回は、香典返しの概要やタイミングに加え、金額相場と向いている品物、マナーや注意点についても詳しく解説しました。香典返しは故人のお通夜や葬儀の参列者に対して渡すお返しの品であり、香典をいただいた参列者に対してのみ渡します。基本的には四十九日を終えてから1か月後までの間に贈りますが、さいきんでは葬儀の当日に渡す即日返しを選択する人も多いです。金額相場は香典の半額程度であり、食品や消耗品などの消え物・白い衣類・カタログギフトなどを選択するのが一般的です。掛け紙は黒白の結び切りを使用し、表書きには志と書きましょう。また、挨拶状には香典のお礼や略儀のお詫びを記載し、句読点や忌み言葉などを避けるのがマナーです。-
 引用元:https://gc-tokyo.co.jp/
ワンランク上のおもてなし!
引用元:https://gc-tokyo.co.jp/
ワンランク上のおもてなし!
世界に一つだけのオーダーメードの葬儀が叶う-
Point
明瞭な料金体系で追加費用が不要
-
Point
ご遺族に寄り添う個別相談と丁寧な対応
-
Point
東京・神奈川に密着し迅速なサポートを提供
-
Point